令和5年度

サッカーにおける競技特異的課題が方向転換動作の運動学および運動力学的要素へ与える影響
河野 達哉優秀論文賞!

【背景・目的】
サッカーではsidestep cutting(SSC)による方向転換によって膝前十字靭帯(ACL)損傷が多く発生している。SSCによる方向転換動作とACL損傷の危険因子に関する三次元動作解析において、方向転換後の競技課題がSSCに及ぼす影響を検討したものは僅かである。本研究の目的は、方向転換後に設定したサッカーに特異的な動作課題が方向転換中の下肢運動学および運動力学的要素へ及ぼす影響を検討することである。
【方法】
対象はサッカー経験のある健常成人男性20名とした。設定条件として、SSCによる90°方向転換後に走り抜けるNormal条件、キックをするKick条件、ヘディングをするHeading条件を設定し、三次元動作解析装置および圧力盤を用いることでSSC実行時の下肢運動学・運動力学的要素について各条件間で比較した。主な解析対象は、膝関節角度および関節モーメント、地面反力(GRF)特性とした。統計学的検討は、各課題における従属変数の正規性に則り、反復測定分散分析もしくはFriedman検定を実施した。主効果を認めた変数に対してはBonferroni補正による多重比較検定を実施し、有意水準は0.05とした。
【結果】
ACL損傷の危険因子と考えられている主な運動学的要素として、足部接地時の膝外反角度 がHeading条件と比較してNormal条件で有意に大きかった。同様に主な運動力学的要素としては、膝外反モーメント最大値がHeading条件と比較してNormal条件で有意に大きかった。また、GRF特性としてSSC実行一歩前の接地における減速力積がNormal条件と比較してKick、Heading条件で有意に大きかった。さらに、SSC支持脚における後方成分最大値がHeading条件と比較してNormal、Kick条件で有意に大きく、推進力積がKick条件と比較してNormal、Heading条件で有意に大きかった。
【考察】
ACL損傷の危険因子とされる要素においては、概ねNormal条件が高値を示した。また、Kick、Heading条件においては、SSC実行後にボールに対して身体を適正な位置に移動させることが要求されるため、SSC実行に先立って一歩前の接地での減速力積を大きくするという動作戦略が生じたと推察される。
中高年者における運動と未病 ―運動を促進する生活習慣・養生を明らかにする―
申 裕成
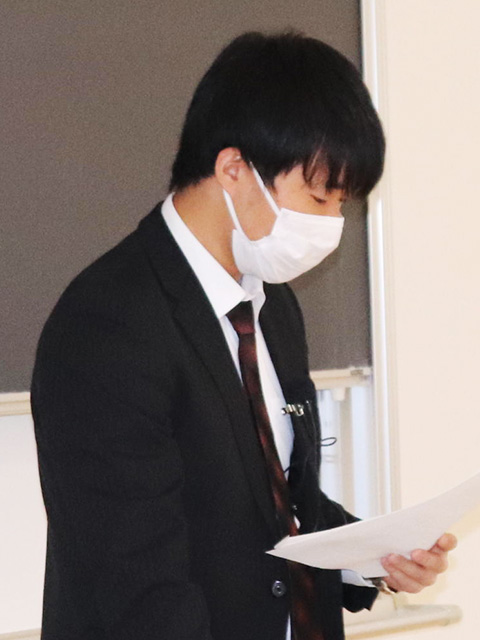
【背景・目的】
一般的に「運動は健康に良い」と周知されているにもかかわらず、実際には運動をしない人が数多く存在し、健康に関する知識と行動の間のキャズム(大きな溝)が生じていることが窺える。本研究は健康づくりの環境を整えることで知識と行動のキャズムを埋めることを目指し、健康な中高年者における運動習慣とその他の体調(未病)や生活習慣との関係性を検討した。
【方法】
「わかやまヘルスプロモーション研究」のデータを用いた横断研究。対象者は2018年7月24日から8月3日に実施された健康診査受診者のうち、既往歴・服薬歴および欠損値のない149名(男性54名:57.0±10.1歳(中央値±四分位偏差)、女性95名:59.0±10.5歳)とし、「血液・尿検査」のデータを除いた全ての健康診査データを探索的に検討した。統計解析は、「筋肉量」に影響する「運動習慣」を結果変数、運動習慣に影響する「体調(未病)および生活習慣」を説明変数、潜在的な「運動促進・阻害因子」を中間因子とした構造方程式モデリング(SEM)によるMIMIC(Multiple Indicator Multiple Cause)モデルの検討をおこなった。
【結果】
SEMの探索的モデル特定化によって「歩行速度」、「自覚的健康観」、「決まった役割」、「近所付き合い」、「規則的な生活」、「漬物、梅干しなどの摂取頻度」を説明変数、「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上」と「中強度以上の身体活動(農作業を含む)」を結果変数、潜在的な「運動促進・阻害因子」を中間因子としたモデルが採択された(GFI:.956、AGFI:.920、CFI:.871、RMSEA:.052)。また、採択されたモデルに「年齢・性別」と「BMI」を強制投入して影響を分析した結果、モデル適合度はやや低下したが、各パスの標準化係数が増加した(GFI:.907、AGFI:.861、CFI:.593、RMSEA:.076)。
【考察】
中間因子は「運動阻害因子」であり、性別とBMIの影響を受けることが示唆された。横断研究のため因果関係の検討ができていないが、生活習慣の改善が運動の習慣化に繋がる可能性があった。
立位の継続により短母指外転筋に対応した脊髄前角細胞の興奮性は変化する
竹内 航平

【背景・目的】
脳血管障害患者は麻痺側手指の筋緊張が背臥位より立位で亢進し、立位の継続でさらに亢進することがある。そこで、前段階として、健常者を対象に背臥位と立位での短母指外転筋のF波の経時的変化と、立位での抗重力筋の筋活動の変化を検討した。本研究は関西医療大学研究倫理審査委員会の承認を得たうえで実施した(承認番号:22-27)。
【方法】
対象は、健常成人16名(平均年齢23.9歳)とした。被験者を背臥位で右短母指外転筋よりF波を記録した。F波刺激条件は、右正中神経(手関節部)に持続時間0.2msの最大上刺激を頻度0.5Hzで連続30回刺激した。F波記録条件は、探査電極を右短母指外転筋筋腹上、基準電極を右母指基節骨底上、接地電極を右前腕掌側部へ配置し、分析項目は振幅F/M比と出現頻度とした。課題は立位条件として、立位の開始直後から10分後で2分間ごとに6試行F波を記録し、立位の継続により生じる姿勢変化と抗重力筋の筋活動を検討するため、F波の記録と同様に2分間ごとに体幹前傾角度と下腿前傾角度および右胸最長筋と右ヒラメ筋の%MVCを算出した。なお、コントロールとして、背臥位でのF波の記録(背臥位条件)を立位条件と同様の手順で日を変えて実施した。統計は、時間経過に伴うF波の変化には反復測定分散分析後のBonferroni法による多重比較、立位条件と背臥位条件でのF波の変化には対応のあるt検定、体幹前傾角度と下腿前傾角度の相関にはSpearmanの順位相関係数を用いた。有意水準は5%とした。
【結果】
立位条件は開始直後より8分後、10分後で出現頻度相対値が増大し、立位条件は背臥位条件より全試行で振幅F/M比相対値と出現頻度相対値が増大した。さらに、立位条件の体幹前傾角度と下腿前傾角度に負の相関を認めたが、体幹前傾角度が増大した例は右胸最長筋、下腿前傾角度が増大した例は右ヒラメ筋の%MVCが経時的に増大した。
【考察】
Schoberlらは10分間の立位姿勢は背臥位より上位中枢の活動が増大すると報告した。本研究でも立位条件は背臥位条件より脊髄前角細胞の興奮性が増大したと考えた。また、Sasakiら、榊原らは、胸最長筋やヒラメ筋の等尺性収縮で安静時より上位中枢の興奮性が増大すると報告した。本研究でも先行研究同様に、8分後、10分後で出現頻度相対値が増大したが、右胸最長筋と右ヒラメ筋の%MVCは低値なため、振幅F/M比相対値は増大しなかった。
JSLH-Diff法における高精度単球算出法の検討
夏原 稜典

【背景】
血液検査分野では、保存可能な標準物質の供給がないため、国際調和プロトコルにより値付けされた新鮮血液を用いて、各基準分析装置のキャリブレーションや国際標準化が行われている。白血球5分類の国際調和プロトコルであるFlow cytometry(FCM)法は、従来法の鏡検法よりも精度が高いが、機種間や施設間で差を認めることが報告されている。その原因として、各細胞集団の不均一性や希少細胞である骨髄系樹状細胞(mDC)、造血幹細胞の出現パターンが不明確であることが、オペレーター間での解析誤差につながると考えられている。特に白血球5分類における単球算定は、mDCを含んだ非常に不均一性な細胞集団であることから、FCM法において、それらの出現パターンを理解し、適切に解析することが重要である。
【目的】
国際調和プロトコル白血球5分類FCM法の一つである、日本検査血液学会白血球5分類算定法(JSLH-Diff法)の単球における不均一性や希少細胞の出現パターンを明らかにし、解析誤差の少ない適切な単球ゲートを設定することにより、FCM法における単球算出法の標準化を行うことを目的とした。
【方法】
健常人ボランティア由来EDTA-2K新鮮血液を用いて、単球およびmDCサブセット検証パネル11color 13抗体(CD45,CD33,CD14,CD16,CD88,CD89, HLA-DR,CD141,CD1c,CD123,CD3,CD19,CD56)と、単球、造血幹細胞およびmDC検証パネル8color11抗体(CD45,CD33,CD14,CD88,CD89,HLA-DR,CD34, CD123,CD3,CD19,CD56)を用いた。
【結果】
サブセット解析では、CD14+ CD16++ Nonclassical単球とCD141+mDCがJSLH-Diff法CD33+CD14+単球ゲートで算出されない細胞群であった。JSLH-Diff法のCD33+CD14+単球ゲートを従来ゲートとし、好中球下限領域まで設定した新規ゲートで比較すると、新規ゲートで0.57%の上昇を認めた。その内訳は、CD88+CD89+単球が0.40%、CD88-CD89-mDCが0.11%の上昇を認めた。造血幹細胞は、新規ゲート内に0.007%出現を認めた。
【考察】
単球のサブセットや、樹状細胞や造血幹細胞の出現パターンが明らかとなった。このことより、新規単球ゲートを用いることにより、解析誤差を軽減し、高い精度で単球の算出が可能となり、自動血球計数装置の精度管理の向上につながると考えられる。
癌性胸水の液状化細胞診検体を用いた形態および抗原保持限界に関する検討
宮内 雅哉

【背景】
近年、細胞診検体を用いたコンパニオン診断が可能となり、シングルセル遺伝子解析も実臨床での応用が期待されている。また、液状化細胞診検体では、残余検体が長期保存可能であり、細胞形態観察や免疫細胞化学染色の施行が可能とされている。そこで、我々は癌性胸水のLBC検体を用いて、細胞形態の経時的変化および抗原保持限界について調査したので報告する。
【方法】
2022年1月から2023年4月の1年4か月間に、十分な沈査量が得られた胸水検体のうち、細胞診で悪性と診断された6症例を対象とした。BD サイトリッチレッド保存液で固定したBDシュアパス標本に対し、パパニコロウ染色と抗体15種類を用いた免疫細胞化学染色を、当日、1か月ごとに6か月間染色した。形態保持の評価は、BD シュアパス標本に経験値のある細胞検査士10名で「可」、「非」の2段階で評価した。抗原保持の評価はセルブロック標本をコントロールとして、染色強度を(-)から(+++)の4段階で病理細胞診専門医とともに評価した。
【結果】
形態保持は細胞の小型化や軽度の細胞質融解化、核濃染化などを認めたが、10名全員が6症例すべて6か月間「可」であった。抗原保持は6症例すべて2ヶ月から3か月で、染色強度の減弱や非特異反応を認めた。
【考察】
シュアパス法で標本作製を行った標本では、組織型により様々な変性所見と思われる細胞変化を認めたものの、軽微な変化であったため、10名中10名が全例で6か月まで判定可能という結果となり、LBC検体の長期保存は有用であると考えられる。また、遺伝子検査でもLBC保存液での長期保存は有用であるという報告もあることから、シングルセル遺伝子解析にLBC保存液で長期保存した検体は有用であると推察する。しかし、免疫染色では症例により3か月以降から染色結果が不安定性を示す染色項目もあり、形態学のみで良悪性が困難な症例に対しては、今回の検討では3か月までが診断を正確に行える限界と考える。
超音波エラストグラフィーを用いた運動負荷後の筋硬度変化と低周波鍼通電が与える影響について
山下 勝大
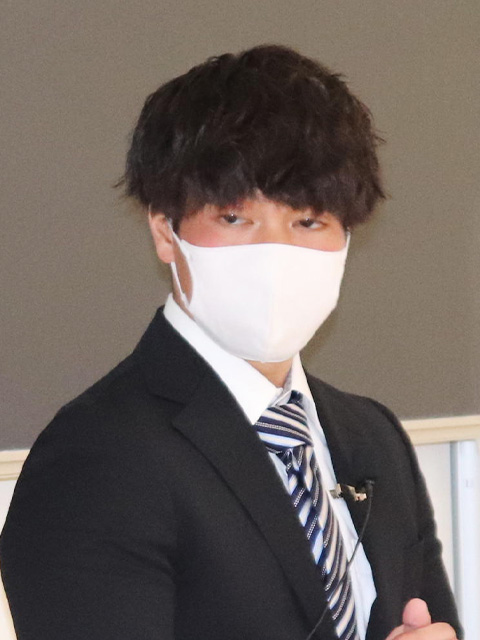
【背景・目的】
鍼治療後に筋緊張が緩むとされているが、客観的な指標を用いて検討した報告は少ない。 近年、非侵襲的に組織の硬さを超音波診断装置によって測定して画像化する超音波エラス トグラフィ(real time tissue elastography: RTE)が開発された。RTEを用いた先行研究 で運動負荷後に筋硬度が増加したことが報告されている。鍼灸臨床では低周波鍼通電がスポーツ後の筋疲労や筋緊張緩和を目的に用いられている。本研究ではRTEを用いて実験1では運動負荷による筋硬度変化を検討し、実験2では運動負荷後の筋硬度変化に低周波鍼通電が及ぼす影響について検討した。
【方法】
実験1の対象は健常成人男性11名(23.4±5.9歳)、実験2は健常成人男性10名(22.1±5.0歳)とした。実験1では腹臥位にて5分間安静後、腓腹筋内側頭最大周径囲部のRTE測定および自覚的な筋疲労感をVASで測定した。測定終了後、片脚カーフレイズ運動を行い、運動終了後、安静15分後、安静30分後にRTEとVASの測定を行った。実験2では5分間安静後、RTEとVASを測定した後、片脚カーフレイズ運動を行った。運動終了後にRTEとVASを測定した後、腓腹筋に位置する承筋穴と承山穴に低周波鍼通電を15分間行い、鍼通電後、通電15分後にRTEとVASの測定を行った。
統計解析はSR、VASの経時的変化についてはShapiro-Wilk検定にて正規性が認められなかったため、Friedman検定を行い、Bonferroni補正による多重比較検定を行った。
【結果】
実験1ではSRは安静時に比べ、運動終了直後に有意に増加した。運動終了直後に比べ、15分後、30分後に低下したが有意差はみられなかった。VASは安静時に比べ、運動終了直後、15分後で有意に増加した。運動終了直後に比べ、30分後で有意に低下した。実験2では実験1と同様にSRは運動終了直後で有意に増加した。運動終了直後に比べ、鍼通電後に有意に低下し、通電15分後においても有意な低下がみられた。VASは安静時に比べ、運動終了直後で有意に増加した。運動終了直後に比べ、通電15分後で有意に低下した。
【考察】
下腿部への低周波鍼通電は片脚カーフレイズ運動により誘発される腓腹筋の筋硬度の回復を促進する可能性が示唆された。
着座動作における体幹傾斜に関する運動の解明
山本 悠介

【背景・目的】
着座動作は、日常生活における身の回り動作の重要な構成要素であり、傷害予防の観点から重要であると考える。臨床上、着座場面で体幹前傾や下腿前傾が乏しいことで異常をきたす症例を経験する。高齢者は若年者と比較して着座動作時の体幹前傾が乏しいといわれており、着座動作を遂行する上で体幹前傾は重要であると考える。着座動作における体幹傾斜に関する運動および体幹前傾と下腿前傾の関係性を明確にすることで、症例の理学療法評価や理学療法の一助になると考え、健常者の着座動作における運動を確認し、関節運動パターンを検討することを目的とした。本研究は関西医療大学研究倫理審査委員会の承認を得たうえで実施した(承認番号 22-29)。
【方法】
健常成人男性24名(平均身長173.0±4.3cm、平均年齢26.8±3.0歳)を対象に、立位姿勢から任意の速度で着座する課題を測定した。動作開始時点は立位姿勢からいずれかの関節運動が1°以上生じた時点とし、動作分析ソフトKinovea(OSS)で確認した。着座動作を2相に分け、屈曲相は開始立位を0%、体幹最大前傾時点を100%、伸展相は体幹最大前傾時点を0%、体幹最大後傾時点を100%とし各相を20%毎に分割した。貼付したマーカーに対して画像解析ソフトImageJ(NIH製)を使用して、20%毎の各部位の角度変化を分析した。統計学的処理は、正規性が棄却されたためFriedman検定をおこないHolm法にて有意水準を調整したのちにWilcoxon符号付き順位検定にて各時点での多重比較を実施した。また、各部位の角度の関係性をSpearmanの順位相関係数を使用して確認した。有意水準は5%とした。
【結果】
屈曲相では立位姿勢(0%)と比較して、20%時点から腰椎部屈曲、股関節屈曲、膝関節屈曲、40%時点から骨盤前傾、60%時点から下腿前傾の増大を認めた。また、20%・40%・60%時点で体幹前傾角度と股関節屈曲角度、60%・80%・100%時点で体幹前傾角度と腰椎部屈曲角度との間に正の相関を認めた。さらに、80%・100%時点で立位姿勢と比較して体幹前傾角度と下腿前傾角度がともに増大した一方で、体幹前傾角度と下腿前傾角度の間に負の相関を認めた。
伸展相では体幹最大前傾時点(0%)と比較して、20%時点から骨盤後傾、40%時点から股関節伸展、下腿後傾の増大を認めた。また、0%・20%時点で体幹前傾角度と膝関節屈曲角度との間に負の相関、60%・80%・100%時点で体幹後傾角度と股関節伸展角度との間に正の相関を認めた。
【考察】
屈曲相の初めは股関節屈曲に伴い体幹前傾し、その後腰椎部屈曲に伴い体幹前傾が増大することが示された。また、屈曲相で体幹前傾と下腿前傾がともに増大したが、体幹前傾が大きく下腿前傾が小さい運動パターンと、下腿前傾が大きく体幹前傾が大きい運動パターンに分けられた。伸展相の初めは膝関節屈曲に伴い体幹後傾し、着殿後股関節伸展に伴い体幹後傾が増大することが示された。着座動作の前方への運動を促すとき、体幹前傾と下腿前傾のどちらの運動を促すべきか評価する必要があると考える。






